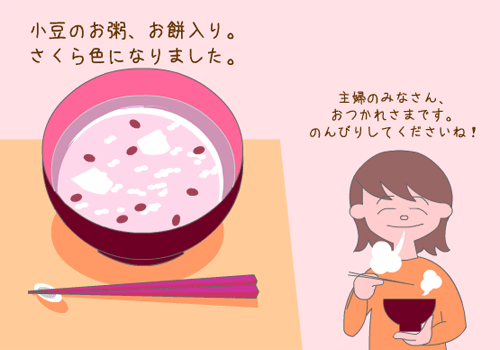あけましておめでとうございます。今年もテーブルコーディネートを学んで発見したことを記事に書いていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
主婦にとって、お正月が一年でいちばん忙しいときでした。
大掃除からはじまって、年末年始のごあいさつ、新年を始める準備、来客のもてなし、お客様が帰ったあとの片付け......。
今年は田部も、休む暇もなく、ひっきりなしにお皿を洗い、洗濯物をたたみ、の一週間でした。いままでの「正月気分」は主婦の働きに支えられてきたのですね。主婦の皆さんおつかれさま。
ふつうの毎日がまた始まって、ほっと一息、インターネットで暦を調べていたら、「小正月」というキーワードに出会いました。
小正月とは昔のお正月のことです。太陰暦が使われていた頃は、その年初めての満月の日をお正月としていたそうです。太陽暦が用いられるようになってから、元旦が正月となりました。元旦から1月7日までを大正月といい、1月15日を挟んだ数日を小正月といいます。行事が今も残っています。
「七草がゆ」1月7日
春の七草(セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ)を加えたおかゆを食べます。春の七草を食べると風邪をひかないといわれていますが、正月中にごちそうばかりを食べて弱った胃腸を休める意味もあります。
「鏡開き」1月11日
年神様にお供えしていたお餅を下げていただきます。大きなお餅を「割る」「切る」では縁起が悪いので「開く」と言います。おめでたい響きですよね。
「どんど焼き」
お正月の飾り、しめ縄や門松など正月用品を集めて燃やす行事です。その火で焼いたもちを食べると無病息災で過ごせるという言い伝えもあります。
「十五日粥」
15日の朝食に小豆を入れて炊いたおかゆを食べます。一家の健康をいのる習慣です。
小正月は「女正月」とも呼ばれているそうです。忙しかった女達をねぎらう意味でそんな名前がつきました。今年は田部も暖かいものでも食べながら、女正月を味わおうとおもいます。