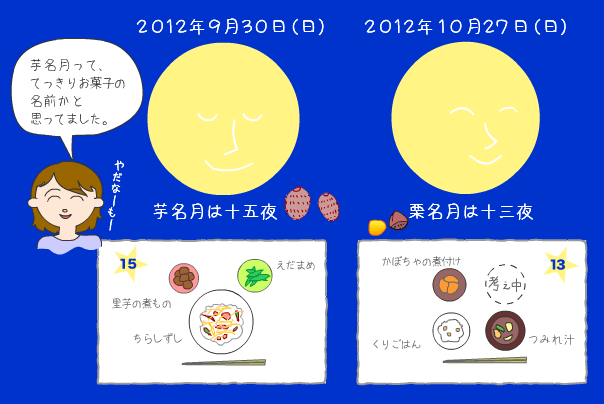ちなみに旧暦の8月15日は、里芋が収穫されるころです。そのため、中秋の名月は「芋名月」とも言われています。
お月様にお供えするお団子は里芋をなぞらえているそうです。わたしも手作りのお団子に挑戦して、すすきと一緒にお供えするつもりです。
インターネットで調べてみましたら、お月見にちなんだ献立もあるある!......枝豆、芋、秋なす、お寿司......卵をお月様になぞらえてポーチドエッグというお料理もありました。
友人がお月見の夜の話をしてくれたことを思い出します。
「子供の頃、お月様にお供えしたおまんじゅうを子供たちがこっそり盗んでいい、という風習があった」ということです。
その夜だけはハローウィンのように、子供たちが家々を回り、おまんじゅう泥棒をしていい日なのだそうです。
縁側にちっちゃな手が伸びるのを大人はこっそり待っていて、おまんじゅうをつかんだとたん、「こらっ!」としかるのがお約束になっていました。おまんじゅうは手作りで家によっていろんな味や形があり、とても楽しみだったと、友人は言ってました。
お月見にはもう一つあって、旧暦9月13日の十三夜は10月27日(土)です。10月の名月は「栗名月」というニックネームがついています。芋も栗も大好物。がぜん、やる気がでます。